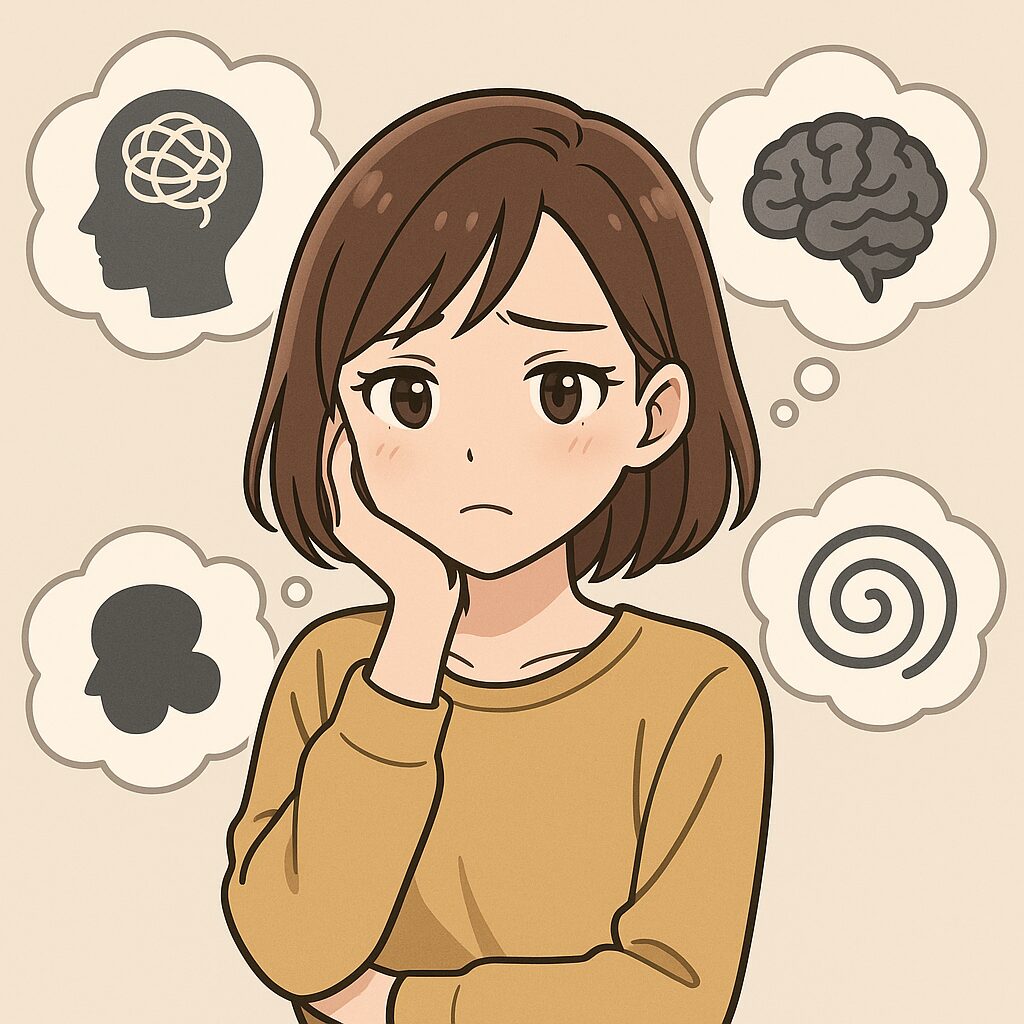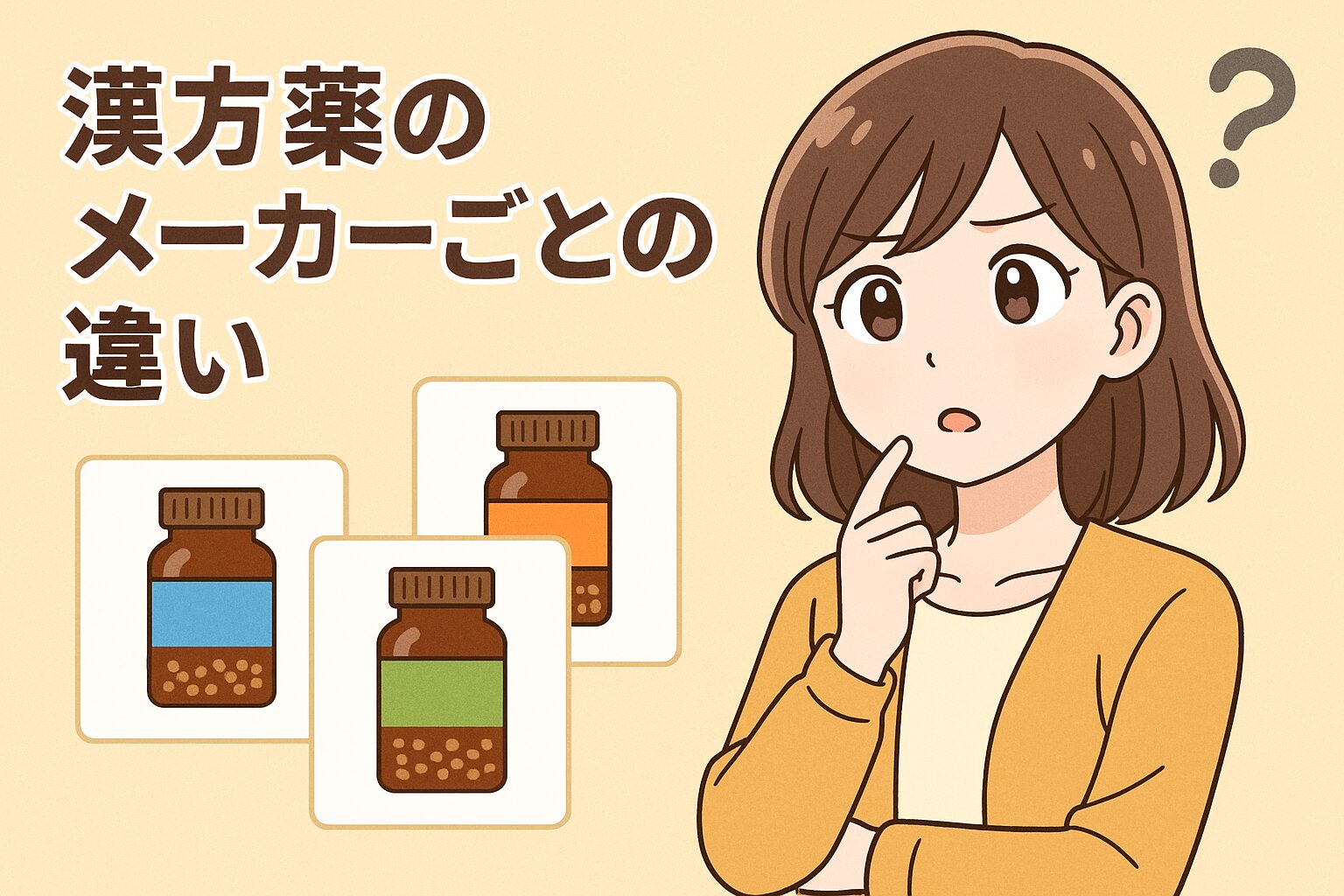もう薬に頼りすぎない!多剤併用を見直す漢方的アプローチ

はじめに:薬が多いのは、よいこと?
日本は高齢化社会の最前線を走っています。慢性疾患をいくつも抱える高齢者にとって、薬は命を守る大切なツールです。
しかし気がつけば、「この人、1日何錠飲んでるんだろう?」と驚くようなケースも珍しくありません。
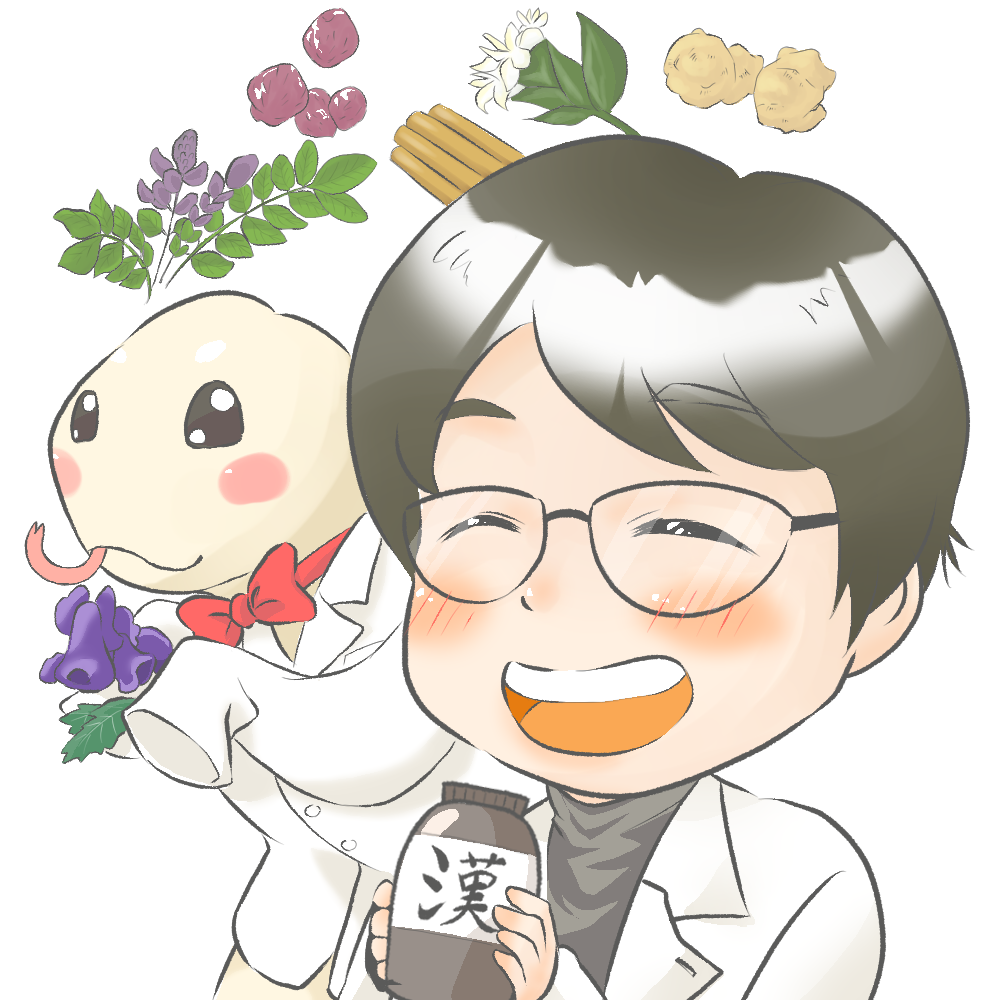
10種類以上薬をもらっている患者さんの自虐話で、「これだけ薬もらってたら薬局を開業できそうやで」という話も時々聞きます。
ここで薬剤師の活躍の場である減薬と言う必殺技が出来ますね。
また後程語りましょう。
こうした“多すぎる薬の処方”をポリファーマシー(Polypharmacy)と呼びます。明確な定義はありませんが、一般的に「6剤以上」の服用があると、ポリファーマシーとみなされます。
問題は、薬が増えることでかえって副作用や相互作用のリスクが増し、服薬がつらくなったり、逆に病状を悪化させてしまうことがある点です。しかも、薬をやめるのは意外と難しい――。
ここに、漢方薬が持つ「多機能性と柔軟性」が注目されています。
そもそも、なぜ薬が増えるのか
高齢になると病気が増えてきます。そして、その病気に対して治療するための薬が増えていきます。
更によくあるのが、薬の副作用を予防するために薬が追加されるといったケースです。
70歳以上での高齢者では6個以上の薬を飲んでいることはさほど珍しくありません。
高齢者に起こりやすい薬の副作用とは?
薬を多く服用することで1個だけでは起こりえなかった副作用が生じたりします。
高齢者に起こりやすい副作用として、
物忘れ、うつ、せん妄、食欲低下、ふらつきや転倒、排尿障害、便秘 などが起こります。
なぜ高齢者に副作用が出やすいのか
まず、薬は口から食道を通って胃や小腸で吸収され、吸収された薬の成分が血液を介して全身に運ばれて目的の場所で効果を発揮します。
また、吸収された薬は肝臓で代謝(分解)されたり、腎臓から尿として排泄されたり、糞便から体外へ捨て去ることで無毒化(薬の成分が毒と言っているのではなく、本来体に存在しないものなので体に影響を及ぼさないように)します。
しかし、高齢者では肝臓や腎臓の機能が年齢や病気によって機能低下してしまうため、先ほどの無毒化に時間がかかってしまいます。
その結果、薬がいつまでも体内に残ってしまって本来の役割以上に効果を示してしまい、効果が出すぎてしまっていわゆる副作用が出やすくなります。
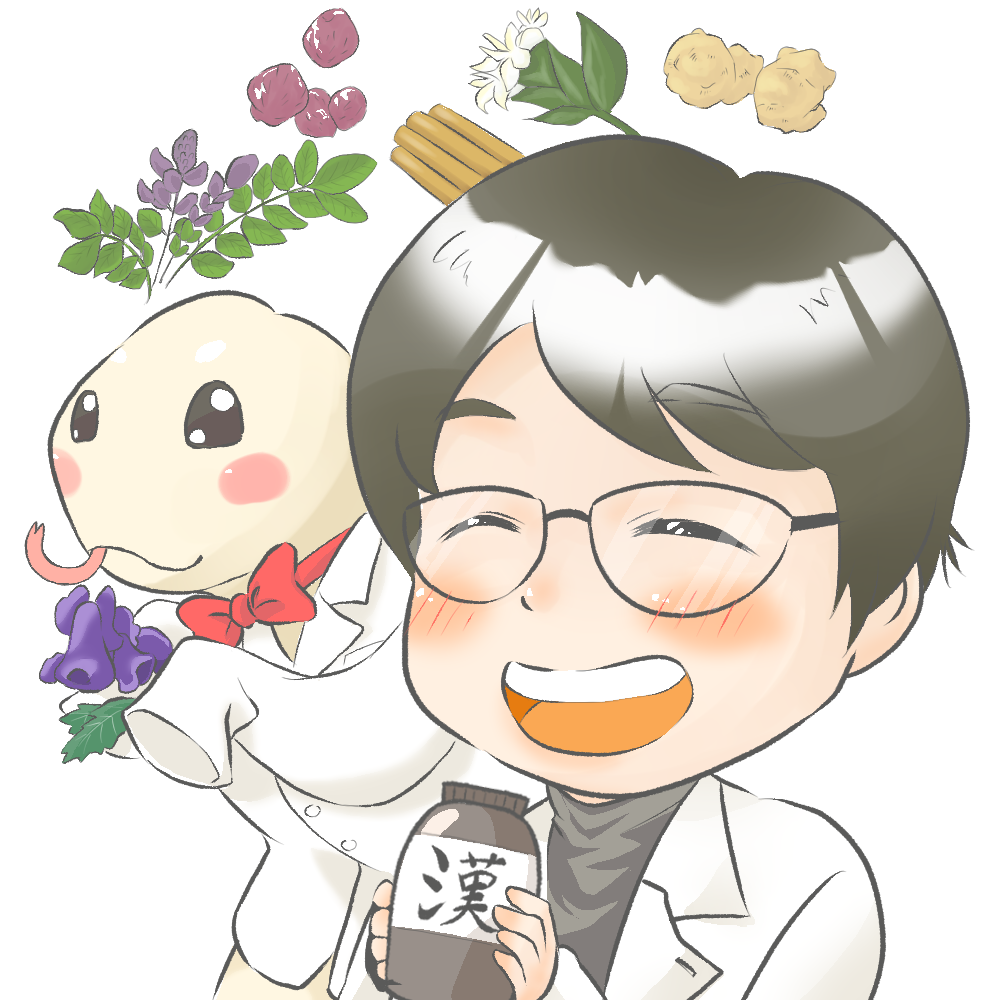
あくまでここで述べている”副作用”というのは患者さんにとって望ましくない効果であって、本来求めている効果とは異なる効果ではありません。
多剤併用のなかで「一処方で複数対応」できる漢方の強み
漢方薬は、ひとつの処方に複数の生薬が組み合わされており、それぞれが違う角度から体に働きかけます。
つまり、「一つの処方で複数の症状にアプローチできる」という特徴があるのです。
たとえば、
- 疲れやすい
- 食欲がない
- むくみが気になる
- トイレが近い
といった症状がバラバラに存在していると、西洋薬では複数の薬剤が必要になることがあります。
しかし漢方では、「証(しょう)」=体質や全体のバランスを見て、ひとつの処方でまとめて対応することが可能です。
例としてよく使われるのが以下の処方:
| 漢方処方 | 対応する症状 |
|---|---|
| 補中益気湯 | 倦怠感、食欲不振、起立性低血圧、風邪予防など |
| 防己黄耆湯 | 関節の痛み、肥満、むくみ、膝の不快感 |
| 抑肝散 | イライラ、認知症の周辺症状、不眠、筋肉のこわばり |
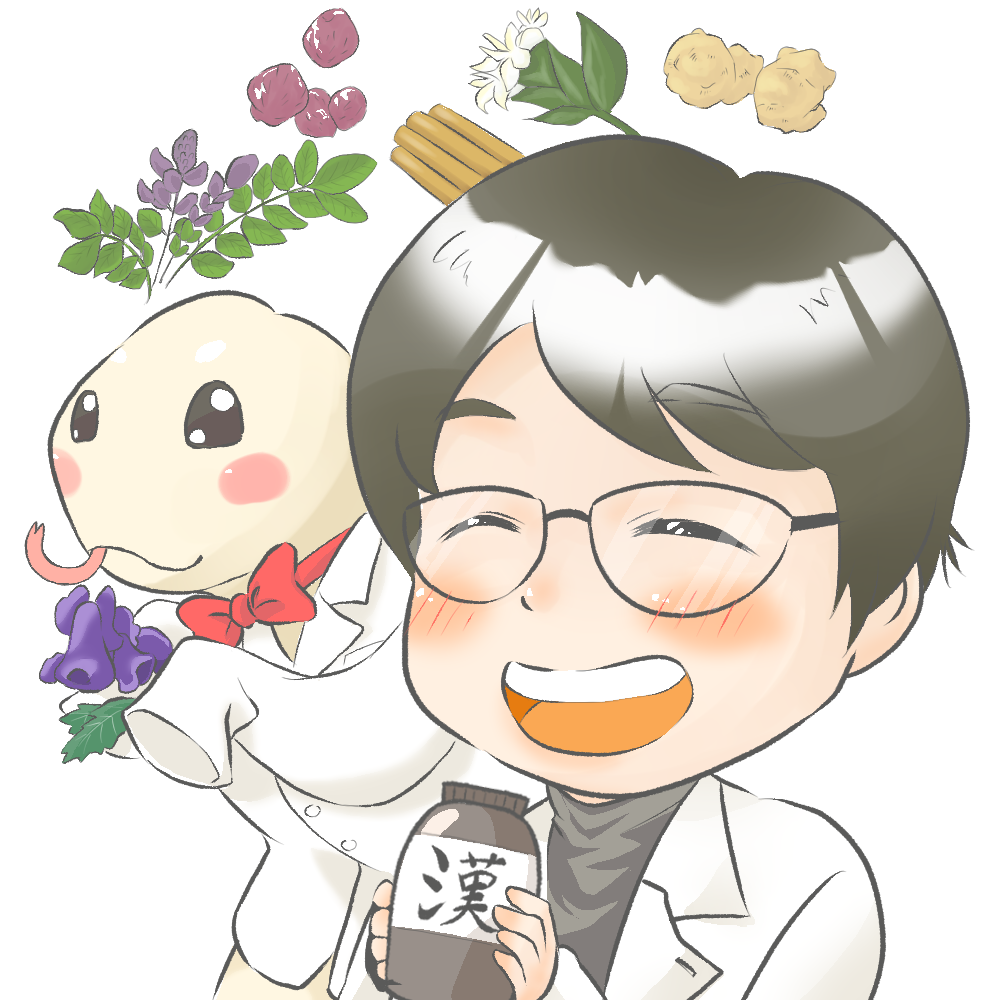
このように、「ひとつの漢方薬で薬の数を減らす」可能性が見えてきます。
ポリファーマシーへの漢方的アプローチ
先ほどの例のような症状を訴える患者さんに対してどうやって薬を選んでいくかモデルケースを提示してお話していきます。
ケース1:関節痛とむくみ
70代の女性。高血圧、変形性膝関節症、糖尿病を持ち、現在5種類の薬を服用中。
- 痛み止め(NSAIDs)+胃薬:疼痛に対して
- 降圧薬:高血圧に対して
- 利尿薬:むくみに対して
- 血糖降下薬:糖尿病に対して
→この症例であれば、
むくみとひざの痛みに効果が期待できる”防己黄耆湯”が使えるかもしれません。そうすれば、痛み止め+胃薬と利尿薬を中止することが出来るので3種類に減らすことが出来ます。
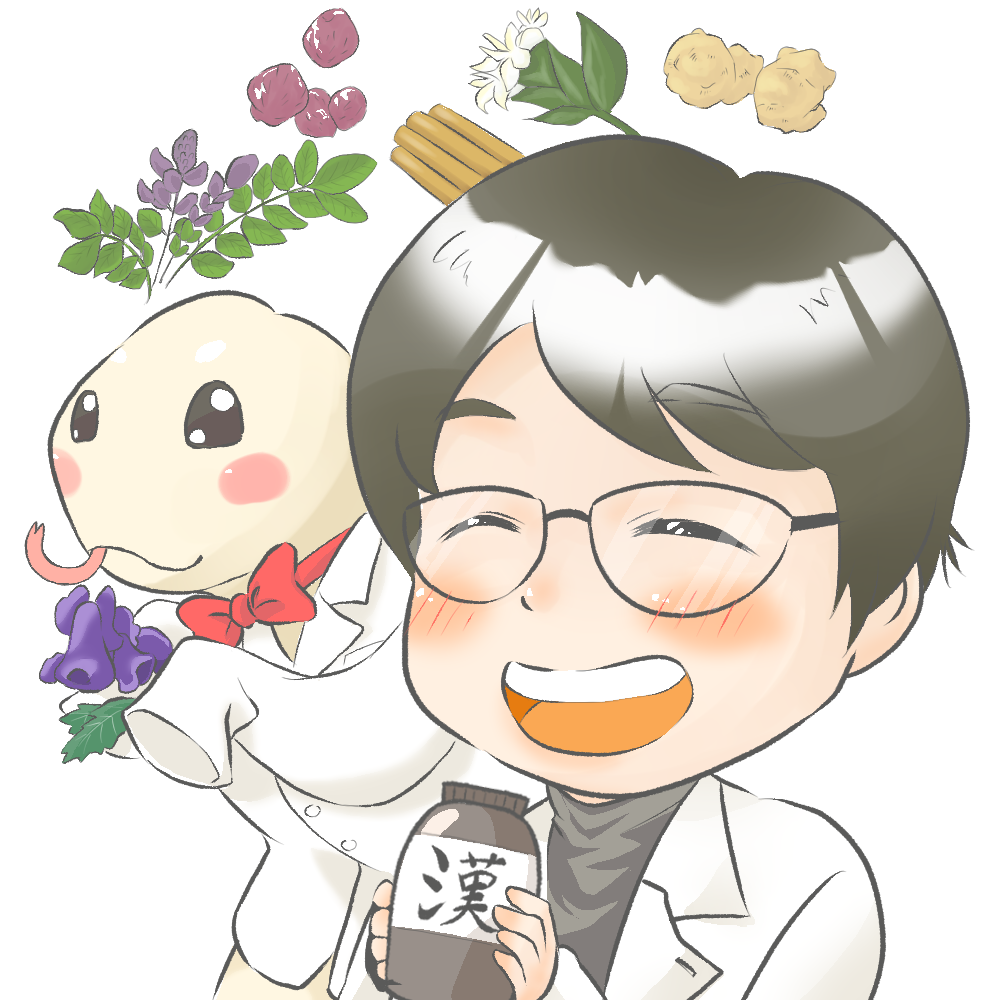
さらに膝の痛みとむくみが軽減して歩行が楽になれば血圧や血糖値も下がるためさらに減薬できる可能性も見えてきます。
ケース2:便秘と不眠、夜間頻尿
80代の男性、夜間頻尿で何度も夜中に起きてしまい不眠が辛く、便秘が気になっている。また、足の冷え・むくみ・腰の痛みやしびれがあり倦怠感も気になっていて、現在6種類を服用しているが、足腰の冷えや倦怠感は良くならない。
- 頻尿治療薬:夜間頻尿に対して
- 睡眠薬:不眠に対して
- 緩下剤:便秘に対して
- 利尿薬:むくみに対して
- 痛み止め(NSAIDs)+胃薬:疼痛に対して
- ビタミン剤:しびれに対して
→男性であればあるあるな症例になってくるかと思います。
頻尿のせいで不眠となり、頻尿治療薬を服用することで副作用の便秘が起こることがよくあります。
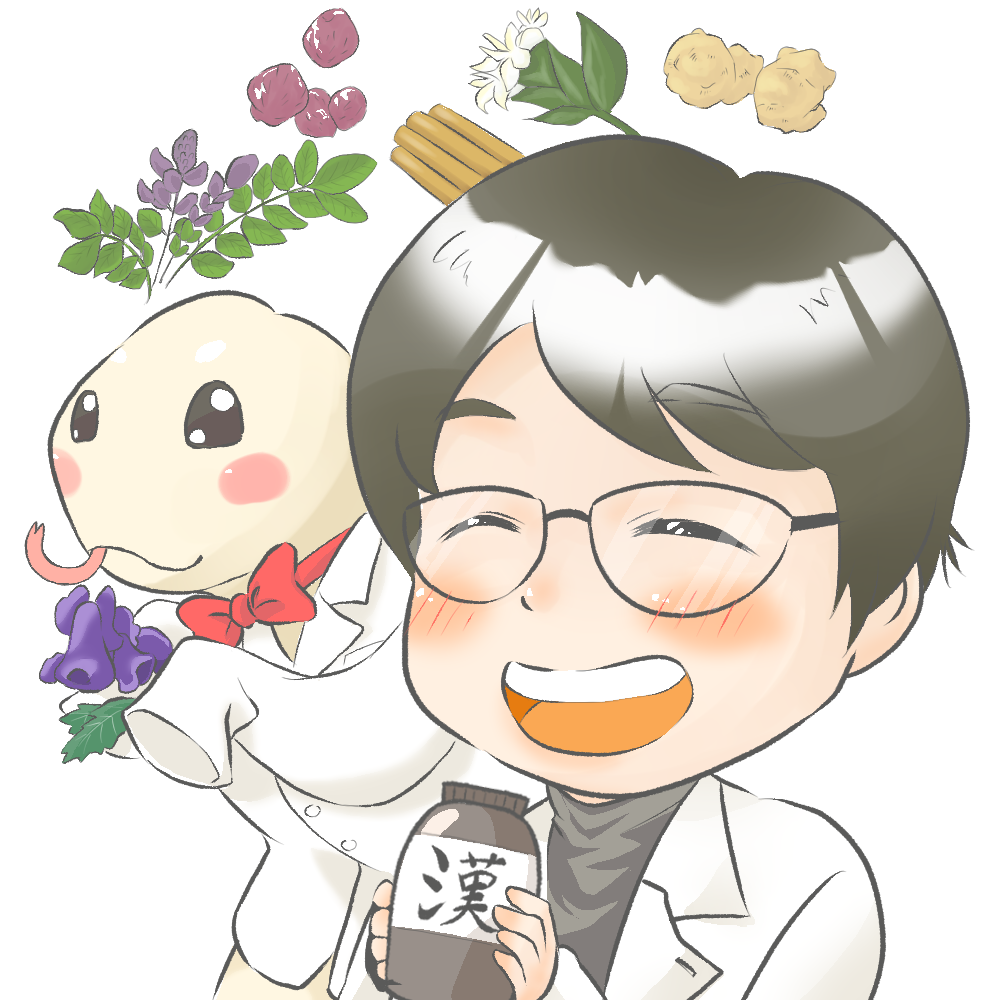
悲しいことかな…西洋薬ではおしっこを止めると便も止まる と言うどうしようもないジレンマを抱えています
これだけ多くの薬を飲んでいてもまだ症状が残る状態…何か救世主はないのか!?
漢方には下肢の冷えやむくみ、しびれ・痛みを改善し、頻尿に効く”牛車腎気丸”があるじゃないか!!!
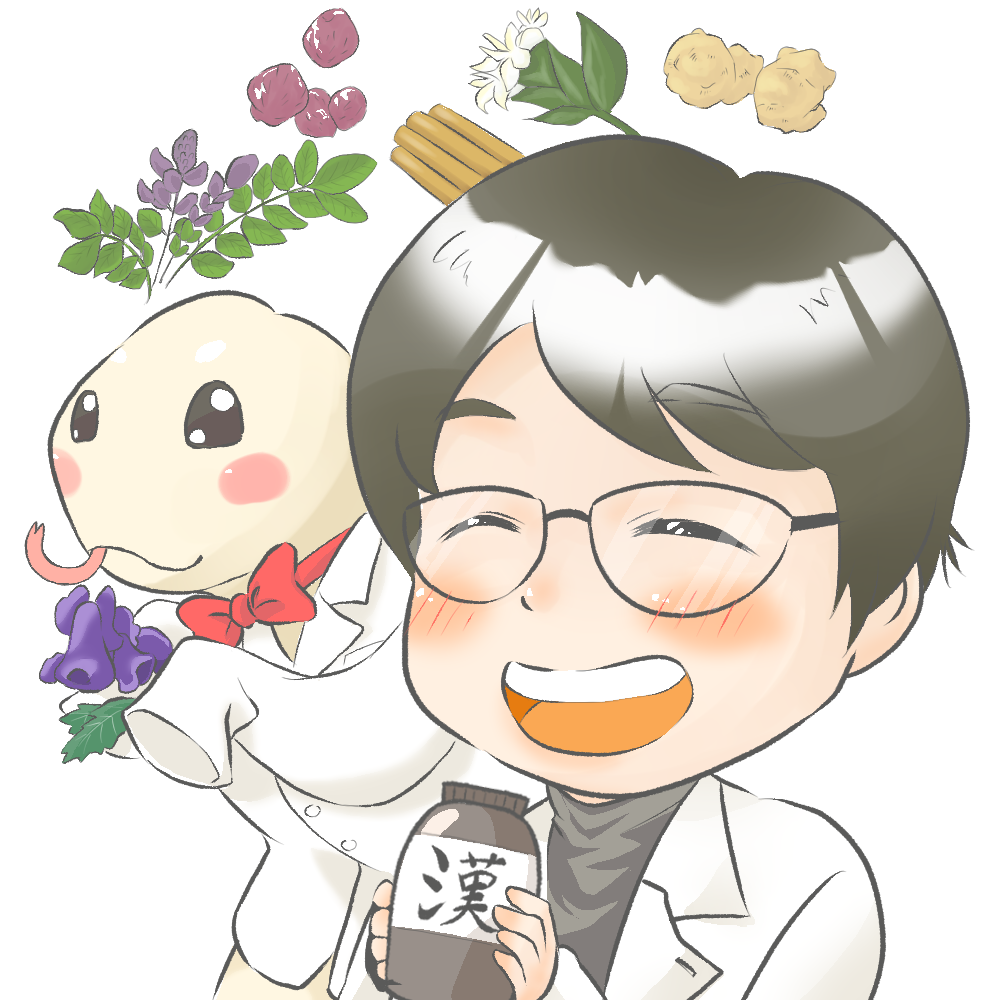
頻尿やむくみを改善することで睡眠薬を使わなくてよくなり、頻尿治療薬による便秘も起こらず、冷えや下肢の倦怠感も改善して、本当に上手くハマれば漢方薬1種類で解決してしまいます。
あくまでモデルケースでピッタリ当たればになりますが…。
注意点
漢方も「安全」とは限らない
誤解してはいけないのは、「漢方=安全、自然、安心」というわけではないということです。
漢方薬も薬であり、副作用や相互作用のリスクがあります。
よくある間違い
- 甘草(かんぞう)の重複 → 低カリウム血症に注意(例:甘草+利尿薬)
→複数の漢方エキス剤を飲むことで甘草が重複してしまうことがある。
→→利尿薬と併用することで低カリウム血症が起こりやすくなってしまう。

- 生薬の薬物代謝酵素への影響(CYP阻害など)→ 西洋薬の効果が変動することも
- 証(体質)に合わないと効果が出にくい もしくは、体調の悪化 → 専門家の判断が必要
したがって、「減薬のために漢方を使う」と言っても、自己判断や民間療法的な運用は危険です。薬剤師や漢方医師と連携して、安全に進める必要があります。
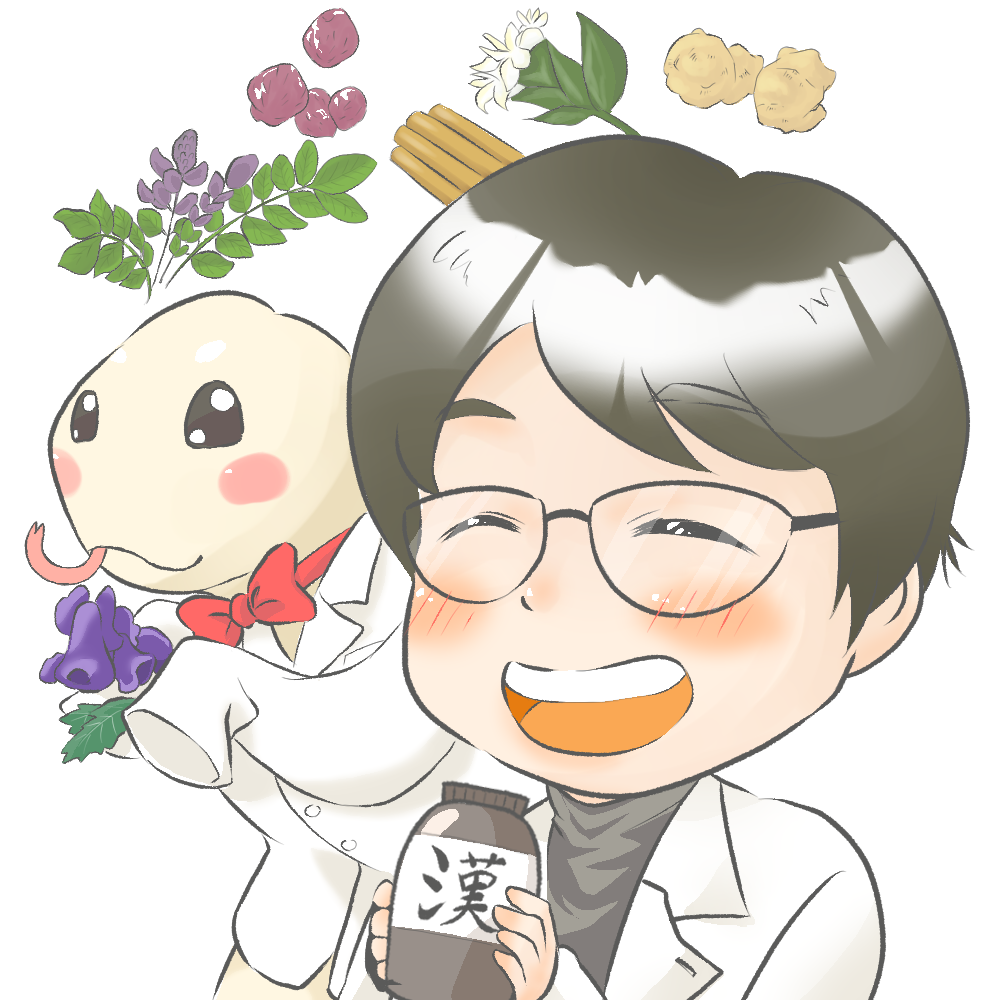
風邪に葛根湯!とか、内脂肪が気になる方は防風通聖散!!!
みたいな、患者の証(体質)を無視した薬の内服は効果がなかったり、重大な副作用を招いたりしてしまうので十分注意が必要です。
チーム医療における漢方薬剤師の役割
ポリファーマシー対策は、医師だけの仕事ではありません。
薬剤師や看護師、栄養士などが連携してこそ、真に効果的な減薬が実現できます。
とくに漢方に詳しい薬剤師は、次のような点で活躍できます:
- 処方薬の成分重複チェック(甘草や麻黄など)
- 証(しょう)や副作用リスクのアドバイス
- 患者のライフスタイルに合った提案(煎じ薬/エキス製剤の使い分け)
- 服薬アドヒアランス(飲み忘れ)のフォロー
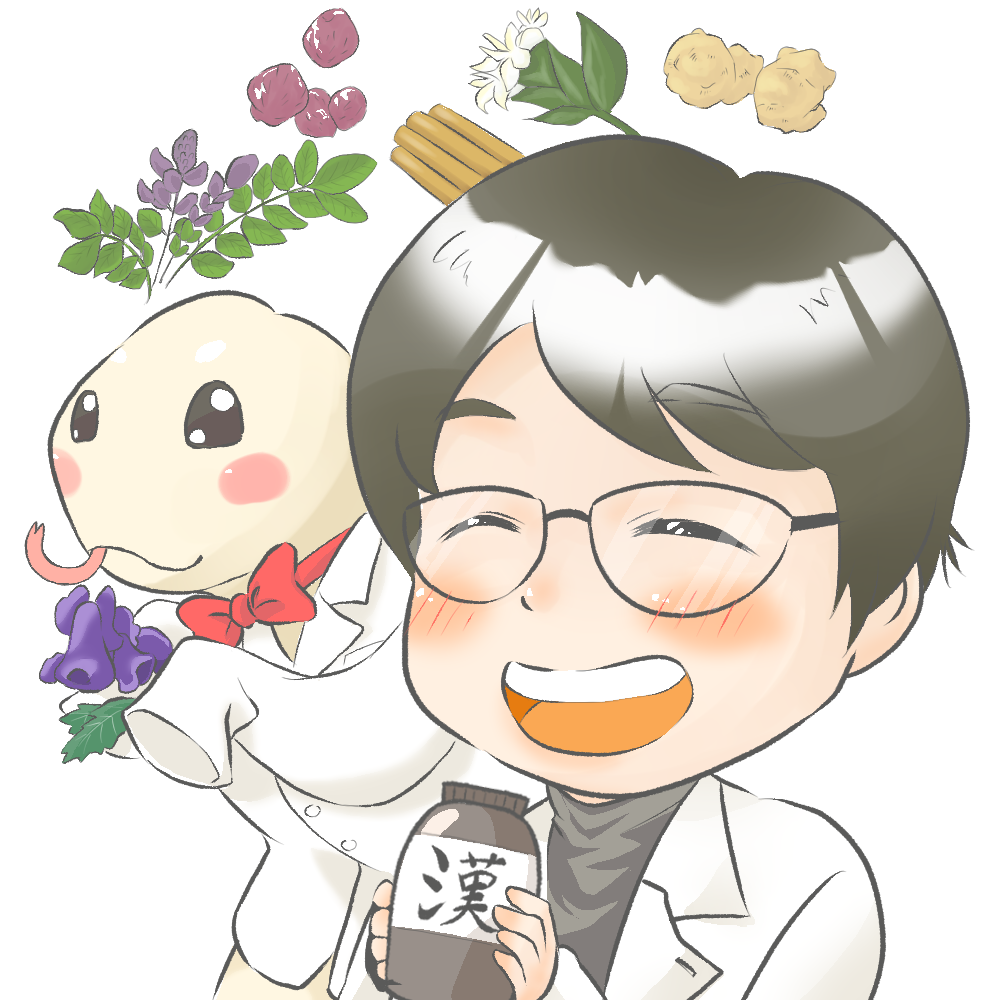
ここの部分を頑張りたいと必死に勉強をしています。
応援お待ちしています!!!
終わりに
ポリファーマシーの問題は、「足す医療」から「引く医療」への転換を求めています。
(薬剤師は引き算が出来る職業とされています)
しかし、ただ薬の数を減らせば良いというわけではありません。
必要な薬を減らしたことによる病状が悪化しては目も当てられません。
それを踏まえた上で、漢方薬は
- 一処方で複数の症状に対応できる柔軟性
- 体質や生活全体を重視する視点
- 西洋薬と相補的な働きを持つ可能性
といった特徴により、減薬と治療の両立に一筋の光を与えてくれる存在です。
“薬が多すぎる”と感じたら、まずは専門家とともに漢方という選択肢を見つめ直してみてはいかがでしょうか?